木造建築は、どうしても話し声などが響いて肩身の狭い思いをすることがあるかもしれない。ここで、少しだけ『防音』といったものについて触れておきたい。
一口に防音と言っても、実際のところ「遮音+吸音」という二つを施すことを言う。全く別の、2つのプロセスが組み合わさってはじめて防音が完成する訳だ。
※音楽スタジオの“防音”は、実は中の音が外に漏れること自体はあんまり気にしてなくて、むしろ外の音が中に入るのを防ぐために防音をしている
■なぜ響くのか
そもそも、なぜ響くのか? 響くとは、一体どういう状態なのだろうか? 音は振動の一種である。空気が振動することで音が波となって伝わる。例えば閉じられた部屋では、発した声などの振動が壁や天井などにぶつかり波形がシンクロする。これにより音が響く。
「自宅の音が響く」なんて気がつかないかもしれないが、賃貸物件を探す際に、何もない部屋で体験できるはずだ。荷物が入り、反射が複雑になることで音が響かなくなる。
これらを逆手に取り、音の跳ね返りをコントロールすることで①自然なリバーブ(残響) ②まったく響かない などの部屋を作ることができる。
■遮音
遮音というのは、文字通り「音を遮る」こと。遮音材は、音を遮るために用意される訳だが、一般に重量が必要、重ければ重いほど良い素材とされる。また、2枚重ねで使われることが多い。
どういうことか? 重量を増すには概ね限界がある。そこで、中空構造にするのだ。中空と言っても、ただの箱型では空気振動を伝搬してしまうため、緻密な計算に基づき振動をカットする。例えばねじれの向きに2枚組み合わせる。とはいっても、配置によっては6畳一間があっという間に消え……これも限度があるね。
いずれにしても木造プレハブは軽く、壁も柔らかいため振動しやすい。このため、コンクリートの打ち壁などと比べて施工ロスが大きく、何重にもする必要が出てくる。
■吸音
遮音は前述の通り、中の音を外に、外の音を中に出さないようにすることができる。対して吸音は「音を吸う」わけではない。どちらかというと、中の音質をコントロールするのが目的だ。残響を減らしたり、跳ね返った振動のシンクロをなくしたり、と言ったコントロールである。
例えば、遮音壁として打ち壁のコンクリートを利用するとしよう。これは正直、お風呂場以上の残響で大変心地の悪いサウンドとなる。そこで、吸音材を組み合わせてコントロールするのだ。この頃では、『防音カーテン』なるものも存在しているので、気になる人はチェックしてみよう。

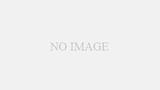
コメント
[…] This post was mentioned on Twitter by ふみへん。. ふみへん。 said: ブログ更新: : 防音とかの話 http://fumihen.info/?p=569 […]