日本が崩壊に向かって歩んでいる。2012年10月末にわかった各社の決算で国内大手企業の大赤字が次々と発覚。「スクウェア・エニックス」「パナソニック」「シャープ」がそれぞれ▲0.5兆円規模、「ソニー」が▲0.1兆円弱だ。日本に何が起こっているのか? 次のラッピング広告を例に話を進めたい。
◯日本終焉の象徴
この広告は新宿PePeの目立つ部分に展開されていた柱へのラッピング広告である。一見おしゃれ、だけどよく見ると変なのだ。この広告にはギター好きには誰しもが違和感を持つ部分が存在する。
パッと見て誰でも気がつくのは「この女の子、撮影現場ではじめて実物のギターを触ったな」「右側のギターアンプってクラシックギターとどう関係するの?」ということだ。しかしことはそう単純じゃない。このアンプ、ビンテージアンプのクローンでわからない人も多いかも知れないが、実は後ろを向いているのだ。
この広告が象徴するのは次だ。
・ホンモノを作る時代は終わった
◯本質こそが大事
「ディテールばっか突っ込んで。そんな細かいところはいいんだよ」と仰られるかもしれないが上記は次のように言い換えられる。
・明確な意図と強い意志で作られてはいない
「ファッション広告だ」「オシャレでそれっぽければいいだろう」。本当だろうか? であればなぜギターなのだ? それこそ不要だったのではないか。あのアンプがメーカーからの借りものでないことを祈りたいし、メーカーの人が気にしないならそのままフェイドアウトしてくれてもかまわない。非常にがっかりだ。
撮影のために近所の楽器屋で借りてきた、とかならもうコンセプトすらないままの間に合わせだね。楽器屋も意見しろよ、と。もしもスタッフの持ち物なのだとしたら「主張しろよ」だ。なにせよこの頃の音楽業界の不振と言えばないため、こうもかんたんに利用されて捨てられている状態に納得が行かない、というのもある。
◯主張が許されない国
要するに立場の強いものに対し、間違っていることであっても指摘がし辛いのがいまの社会なのだ。これは年功序列が多いにはびこっていることをよく表している。つまりね、どんなに素晴らしいアイデアも年齢と地位と好き嫌いだけであっさりと判別されてしまうわけ。ここにひとつ、大きな問題がある。誰もが間違うことはあるわけだが、それにブレーキや補正をかけられる人がいないということ。
賢くステップアップする人は見事なほどトップの性格を見抜いて、気に入られるよう嫌われないよう、それと感じさせずに煽てるのがウマい。つまり、トップの出す方針がどんなにズレていてもブレていても、それについていく人がトップの左右に立ちはだかることになる。だから反論は絶対に届かない。ストッパーは、存在はするが機能しないのだ。
◯新しいアイデアが出ない
新しいアイデアは、大抵の場合潰される。なぜならマーケティングの結果が「今までどおり」を示しているからだ。したがって体制のこともあってそのようなものは登場しないし期待もできない。結果、家電の開発は「勝手に氷ができる」とか「かんたんに録画予約ができる」とかディテールを掘り下げることになる。
国内に小さな需要があるのは明白だ。キャッシュが欲しい。だから、どのメーカーもギリギリの開発費でどうでもいい機能を躍起になって議論し実装することに勤しむ。流通が定めた商戦のタイミングに合わせて完成を目指すことになり、それによって各社の商品が店頭に並ぶ。しかしどれも本当に「ちょっとの差」なので価格競争に陥りコモディティ化が進む。ちょっと待て、と言いたい。
◯日本がヤメるべきこと
私は以前に「iPhone以前はまともなOSが搭載されておらず、端末の見た目はよくても中身がまったく足りてない」ということを書いた。「機能はスゴいけど使うのに取説がいる」だとか「カメラの起動すらどこを押せばいいのか」とか気に入らない点が満載だった。スペックばかりで使いにくいうえに電池ももたないので途中で解約してiPhone3Gを購入した。
日本の端末開発現場ではOS開発といった意見も出ていただろう。もしくはあったかも知れないが「これまで売れているのにOSが『ダメ』ってどうして言い切れる?」というような議論があったのかもしれない。とにかく、なにもしなかった。この辺りが本当にダメなところで、こんなものは詭弁だ。にも関わらず、使っていれば微妙だと感じる点も予算や議論であっさり消滅する。「売れているものこそ正義」だからだ。そしてiPhoneが登場し端末はよりソフトウェアを作り込む時代へ突入した。
こうなると今度は思い切りどうでもいいディテールを掘りはじめる。Androidから操作できる冷蔵庫など誰もいらないのだ。そんなものよりも、もっと大枠をがっちり作り込むべきなのだ。考えてみても欲しい。端末やウェブアプリが勢力を挙げてきたのは「ユーザーにとって必要だった」からなのだ。
◯神話崩壊、技術力の低下
日本の技術はスゴい。確かにそうかも知れない。だが、本当だろうか? 例えば、まことしやかに囁かれる「農業はナンバーワン」だが私はそうは思わない。技術がきちんと伝承できておらず年々作物の味が落ちているという。
私は同じことを工業にも感じている。職人たちの技術は伝承されていないため現在の鋼鉄技術を持ってしても1600年代のような切れ味の刀が作れないというのだ。日本はアウトソーシングにこだわり、気がつけば中国や韓国を育てた。
いま、その技術力は韓国や中国にある。低コストが魅力の生産力は、ただ低コストだけでなく品質にも高い信頼がおける。アップルをはじめとするシリコンバレーのメーカーが鴻海(ホンハイ)精密工業へ発注をするのもそこにポイントがある。
ところが日本はここにきて液晶を受注するだとか、鴻海と提携するだとか下請けへ甘んじようとする流れになっている。せっかくここまできたのだ。もう一踏ん張りではないか。
◯日本が向かうべき未来
ユーザーへ提供することの意義とはなにか、考え抜くべきだ。端末の話に倣うならば「売れているものが本当に正義なのか」を真に問うべきである。誰もが顧客になりうる時代で、自社の社員こそ最も近い位置にいる顧客である。彼らを徹底して手厚く扱うべきなのだ。そして、彼らの意見から本質を見抜き、それを製品に反映させる。それができる本当の組織作りに勤しむべきである。
時代の刀鍛冶の如く、ディテールを突き詰め切れ味の鋭い刀を研ぐ、そんな力を養うべきだ。そうして得た技術力を本質に注ぎ込むのだ。利益を得るためではなく人々の生活を豊かにするために、である。
アップルのスティーブ・ジョブズさえも魅了した、あの“ウォークマン”をもう一度作れないか。


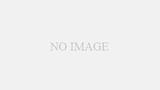
コメント