公募で決まったオリンピックのエンブレム。佐野研二郎さんの次々と浮き彫りになる“盗作疑惑”でとうとう取り下げが確定的に。
2020年東京オリンピックのエンブレムについて、大会の組織委員会は佐野研二郎氏のデザインしたエンブレムの使用を中止する方針を固めました。このあと臨時の会議を開いて、最終決定することにしています。
この記事を執筆中の現在時刻23時までに「盗作を認めた」とか「本人のコメント」とかがすでに出回っておりますが、個人的にもずっと制作畑なもので少々思ったことを。
まず佐野研二郎さん。この方、私は存じ上げない方ですが、どうしてなかなかの輝かしい功績じゃないですか。大手企業が重宝したデザイナーさんですから、きっと納期がしっかりしてて、意図した通りのものを高いクオリティで作ってくれる、任せておけばいい感じにしてくれる、そんな信頼ある人物だったんでしょう。それがここまでボロボロと剥がれ、皮膜が残らずこぼれ落ちてしまうと本当にメッキだったとしか言いようがないですね。
彼を育てた人、彼を信頼していた人、いろんな方が周辺でサポートしてきたのだと思うのです。あれだけ大きな案件ばかりを担当しているのですから、そんな周囲の依頼側に立つ発注者の皆さんも、きっと高給取りでしょう。だけど、その給与を使って何を勉強してきたの?というのが率直な感想。要するに節穴としか言いようがない感じがします。
テクノロジーの進化は凄まじく、本当にものスゴい発展を遂げました。自分の身の回りの35年のことだけを考えてみると、本やテープ、CDなどの媒体が成長軌道に乗った1990年代、その合間を縫うようにMacが誕生しWindowsがその座を取って代わってDOS/Vが全盛になりました。しばらくしてメディア産業が成熟期を迎えると同時に通信技術が発達しました。しかし携帯端末が登場し、それがiPhoneに取って代わっても、人が見るもの、楽しむもの、取り扱うものは、そう大きくは変わらない。すなわち、全く新しいものを育むことはそれくらい難しいことなのだと思います。
音楽において同じようなことをずっと思っていたのですけど、例えばメロディのパターンって限られてくるのですよね。
- ラシドレシーソラーの例(YouTubeより転載)
ケーデンス(カデンツァ)などもそうですが、なんならクラシックとジャズで大抵のパターンが出尽くしてるし、もうこれ以上は意味のない音の羅列のような気がしてくるわけ。どういうことかというと、一般に認知されるメロディとかコード進行——いわゆる「パンピー受けする楽曲」って観点で絞り込みをかけていくと、「新しいものを作る」なんてもうほとんど夢物語だと思うのです。
辛うじてコンテンポラリージャズシーンの一部のアーティストがそういう世界を構築しようと努力しているわけですが、あるいは現代音楽の作曲家が果敢にチャレンジしているわけですが……そういう音楽を聴く人もまた圧倒的に限られる、すなわち一般には理解され難い世界です。
そのような観点から考察すると、オリンピックのエンブレムのような商業作品において最も重要なことは1人でも多くの人に『それ』と認知されるものでなければならないわけで、それがそれ足らしめるに至る裏付けを如何にわかりやくく伝わりやすく提案できるか?がポイントなんです。しかし、今回の騒動の場合は半ば芸術作品のようなものが選定されており、選定のポイントからしてズレているような気がしてなりません。なぜ彼の作品を選んだのか? これが世界に「『日本』のエンブレムは和的で素敵だ」と感じさせるデザインだったでしょうか? これらは是非とも先生方のご説明を願いたいもの。また仮にパクリじゃなくベルギーの劇場のあれをモチーフにしたのだとして、なんの意図があったのか? どんな角度から見ても全く伝わらないでしょう?
優れた芸術家は盗む
上記はスティーヴ・ジョブズの弁だけど、盗んで刺されて凹んでいてはね〜。
やっぱり盗作でしたという結末。全く新しい『T』を作ろうというのに、世の中に溢れ返るTを見ていては、何が生み出せるものですかね。きっと、『制作』『著作物』というものの在り方を変えねばならない、そんな転換期に入ったのではないでしょうか。お隣の中国や韓国をパクリ文化と笑ってはいられないのです。
佐野さんには是非とも、今後の日本文化のために前を向いて後進の育成に従事してほしい。この経験を伝えてほしい。こんなことに苦悩していないで前進いただきたい。

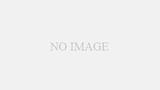
コメント